本日は、評価損益(含み損益)に対するわたし自身の考え方や捉え方を書いていきたいと思います。
さっそくですが、わたしは評価損益は利益が確定したものではなくいわゆる「未実現利益」であることから、「資産が増減した」とは捉えないようにしています。
ネットやYouTubeなどを見ていると、近年は相場が良くて株価が上昇局面にあったことを背景に、資産が「5,000万円になった」や「1億円になった」といった投稿などを見かけることがあります。
わたしも先週末時点で含み益が+1,432万円あり、これにより世の中一般としての金融資産は7,515万円あります。
しかし、株式市場は水ものであり、現在の株価水準が実力どおりなのか水膨れしたバブルの要素をはらんでいるのかは誰も正解が分からないと考えられることから、含み益である+1,432万円は自身の金融資産と捉えて良いとは自信を持って言い難い心境です。
2009年度での初投資(ETF)
わたしが初めて個別株を取得したのは2015年度ですが、資産運用という点でいうと、2009年度に日経平均に連動(たしか)するETFを購入したのがスタートでした。
当時はなかなか相場が良くならず、30万円分を買って△1~2万円の損失を出して売却した記憶があります。
しかし、その後東日本大震災が起きて日経平均が6,994円まで暴落した状況であったなか、「さすがに下がりすぎでは」と思い、たまたま上昇基調に転じてちょっと経ったタイミングで、2009年度に買ったものと同じETFを8,000円台で購入して、その後+4~5万円のプラスを確保して売ったように記憶しています。
2009年に出した△1~2万円の損失と合計して、+3万円ほどの利益になったことを覚えています。
2015年度からの株式投資
東日本大震災後でのETFの売買によってネットで+3万円程度の利益を出して以降は、しばらく投資はしていませんでした。
しかし、徐々に貯金額が増えていくなかで資産運用しないともったいないと感じるようになり、2015年度から個別株を対象とした株式投資を始めました。
当時の日経平均株価は17,000円程度であり、現在の日経平均株価の半額にも満たない水準です。
初めての個別株の投資では、約110万円程度を原資にして6銘柄を取得しています。その際には、三井物産(8031)を1,350円で取得していたり、MUFG(8306)を527円で取得していたりします。いずれの株価も現在は2~3倍を超える水準まで上昇していて、今では考えられないような安値で取得することができていました。
コロナ禍以降の株価上昇
上述のとおり、現在は含み益が+1,432万円(取得額対比+40.93%)ありますが、含み益が大きく増えたのは2020年度になってからです。
コロナ禍では経済を循環させるために政府や日銀が資金を大量に市場に流しました。
市場でダブついた資金が株式市場に流れて株価の押し上げに繋がりましたし、日銀も大量のETFを買って市場を買い支えるようなこともしましたね。
これによって2020年度は日経平均株価も2万円程度で開始しましたが、2023年度には3万円を超える水準まで上昇しました。
また、2024年から新NISAが開始されたことにより、一層の個人マネーが株式市場に流れ込むことになったかなと思います。
米国では急激なインフレが進行して政策金利が高止まりしていたため、日米の金利差によって円安が進行したことで日本企業の業績好調をにらんで株価が上昇したといった面もあるかもしれません。
要因は多々あるかもしれませんが、いずれにしても2024年度では日経平均株価はさらに上昇して4万円を超えています。
評価損益(含み益)の考え方や捉え方
ここまで書いてきたとおり、わたしは2009年度に少額ながらETFを触り、2015年度から本格的に株式投資を開始しています。
そのなかでは日経平均株価が1万円未満の環境下での投資を経験していますし、その後4万円を超えるまでの成長を経験しています。
そうした経験を背景に、日経平均株価が現在のように4万円前後に居座る状況に慣れておらず、現在の含み益が水膨れしているように感じられるところがあります。
まあ、本当に「水膨れしている」と信じて将来の株価下落を見込むのであれば、今は投資を控えて現預金を厚めに持ったうえで、実際に株価が下落した局面で株式を買い進めるという戦略もあるかもしれません。
しかし、年間400万円を新規投資する計画のもとで7年後での「Fireable」を目指すこととしていますので、そういった相場観に基づくタイミング投資のようなことは行わず、毎年計画どおりに新規投資を積上げていくことにしています。
途中からやや脱線してしまいましたが、性格的にも保守的に考える面があったり、計画を立てたりシミュレーションしたりすることが好きであったりもするなか、評価損益を資産額に含めて考えてしまうと計画が暴れてしまい見通しが立てられなくなってしまうことも含めて、評価損益は資産には含めて考えないようにしています。
評価損益(含み益)が増えたらうれしいか
とここまでは評価損益が改善して含み益が増えてもあまりうれしい気持ちがわかないような書き方をしてきました。
しかし、実際には含み益が増えるのは大変うれしいというのが本音です。
というのも、含み益が増えるというのは投資先の株価が上昇しているということであり、企業の業績が好調に推移していることの表れでもあります。
業績が好調であれば増配によって配当金が増える可能性にも繋がります。
また、足元では「金利ある世界」の復活により元本割れリスクのない銀行預金にも一定程度の利息が付く時代になってきましたので、リスクフリーな銀行預金と元本割れリスクのある株式との間でリスクプレミアムが生まれるような市場原理が働いて、企業に対する増配圧力が増すことになったりしないかなと期待していたりします(とはいえ教科書的に言えば、リスクプレミアムは配当だけではなく株価上昇期待によって説明することも可能であるため、増配圧力が増すことには繋がらないかもしれませんが…)。
最後に
ここまで長々と書いてきましたが、シンプルに言うと「含み益があっても資産としては捉えない」けれど「株価上昇による含み益増加はうれしいし期待したい」といったところでしょうか。
投資先の企業には今後も頑張って株価を上昇させてほしいなと思います。
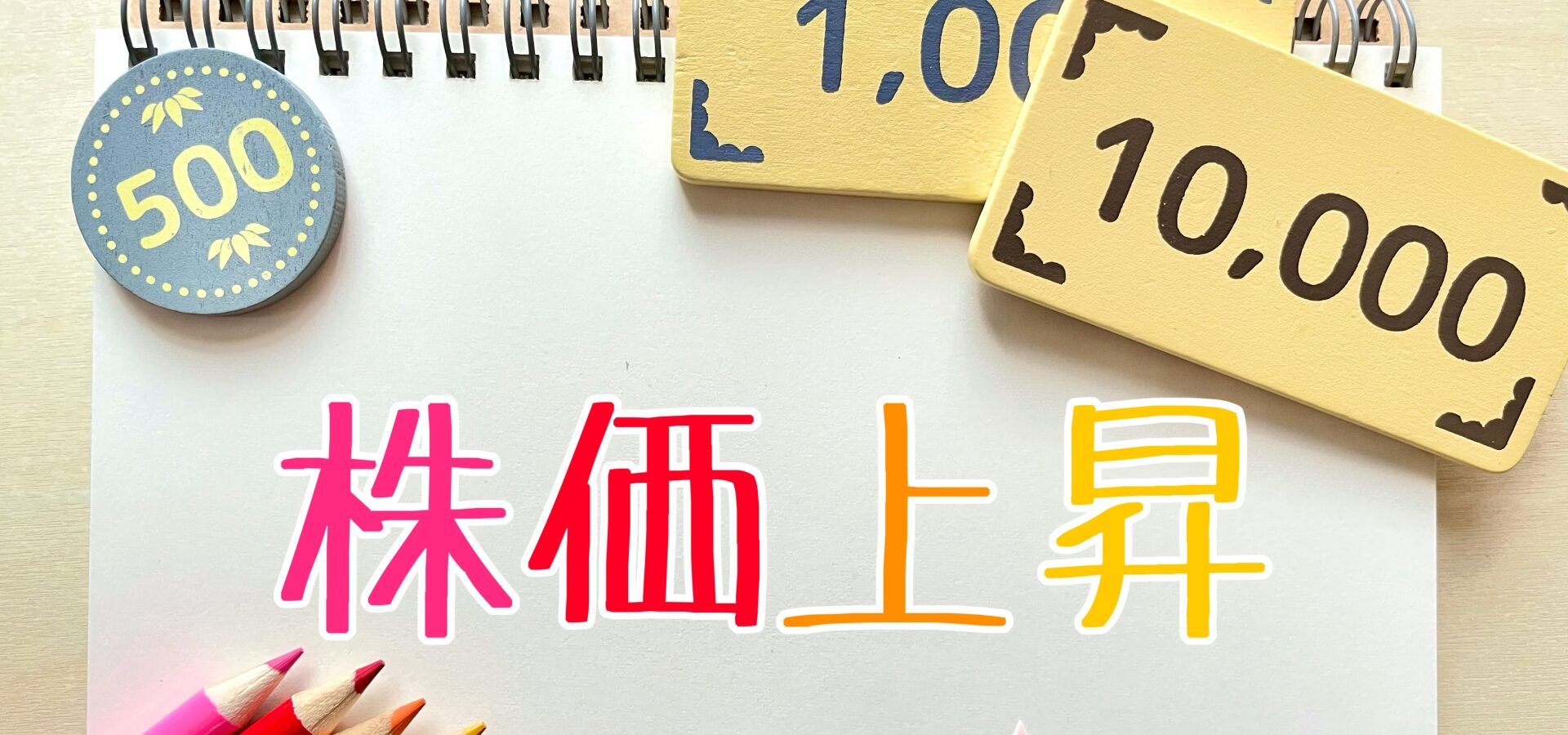
-e1750861693764-120x68.jpg)