これまでは現在の資産状況や今後の目標を書いてきたところですが、本日は株式投資における方針のようなテーマを書いていきたいと思います。
6月末時点での株式投資額は取得額ベースで3,487万円、61銘柄であり、高配当株で構成しています。
世の中的にはインデックス投資(S&P500やオルカンなど)の方が資産形成を進めるうえでは効率的であるとされています。
投資をしている人達の間では「敗者のゲーム」という書籍が非常に有名です。
ざっくりと言えば、数十年に渡って投資を行う場合には、「勝ちを拾う」のではなく「負けないこと」が何より重要であり、インデックス投資によって負けを回避することができると書かれています。
アクティブファンド(インデックスを上回ることをベンチマークとして攻めの銘柄構成にする)は短期的にはインデックスよりも優れたパフォーマンスをあげることはあっても、10年単位などで考えるとインデックスを上回ることがほとんどないとの実績が示されています。
また、インデックス投資は配当金という形で利益が吐き出されることがなく、基準価額に内包されていきます。これにより、配当金の形で利益が出るたびに税金を取られることもなく、その点でも効率的であるとされています。
わたし自身は、上述のインデックス投資の効率性の高さを理解したうえで、インデックス投資を行わずに高配当株を投資対象としています。
ここからは、なぜわたしはインデックス投資ではなく高配当株投資を行っているのかを記載していきたいと思います。
1 実現利益と未実現利益への分解可能性
わたしが高配当株投資を行う一番の理由は、高配当株による利益が「配当金としての実現利益」と「値上がり益としての未実現利益」に分解可能であることです。
インデックス投資やバリュー株投資による値上がり益は、売却して初めて利益が実現しますが、逆に言えば売却しなければいつまで経っても利益は実現しません。
株式は「買うタイミングも難しい」ですが、それに加えて「売るタイミングも難しい」とも言われています。
売却して利益を確定させるまではキャピタルゲインはあくまで未実現の利益ですので、わたし自身は「利益が出ている」や「資産額が増えた」といった捉え方は考えないようにしています。
株価が上昇すれば当然うれしくはなりますが、将来的に株価が下がった場合のいわゆる「含み益バリア」として盾になってくれるぐらいのものとして考えています。
これに対して配当金は完全な実現利益です。
わたしは毎年の株式投資額を「給与所得からの400万円+配当金」としたうえで、配当利回りは税引後3%以上を条件に新規投資するルールとしていますので、将来の配当金受取額をシミュレーションすることが可能です。
具体的には、45歳時点では294万円の配当金の受取りを見込んでいますし、その後は投資のペースを緩めたうえで50歳時点で373万円の受取りを見込んでいます。
配当利回りを税引後3%としている点は強気かもしれないとの不安は残りますが、増配を一切織り込んでいない点は極めて保守的であるとも思っています。したがって、計画どおりに着実に新規投資を積上げていけば見込みどおりの配当金をもらえるのではないかと考えています。
ここで改めてインデックス投資を振り返ってみると、インデックス投資は売却するまではひたすら未実現利益を積み上げていくことになるため、将来的な実現利益の水準を見通すことはそう簡単ではありません。
これはひとえに、高配当株投資が実現利益と未実現利益に分解することができるのに対して(配当金と値上がり益に分解)、インデックス投資は実現利益が見えないところですべて未実現利益に内包されてしまい分解できないことによるものだと考えています。
ただし、実はそうは言っても高配当株投資もインデックス投資も本質的には変わらないと捉えることができるとも考えています。
というのも、高配当株投資も値上がり益を見通すことは困難ですので、配当金と売却益を合算した実現利益の見通しを立てることは困難です。
また、インデックス投資も「毎年3%は分配金があり再投資している」と捉えて自分なりのバーチャルな基準価額を計算すれば、分配金と値上がり益に無理やり分解することは可能ではあります。
しかし、近年は各社増配傾向にある状況下、高配当株投資では配当率は税引後3%から上昇傾向にありますし、不況になれば減配の可能性もあります。そうしたなか、高配当株投資であれば単年度で配当金受取の実績が出てきて実数として分解することができるため、分解がより正確になります。
配当金に増減があれば将来の計画を見直しすることもできるため、シミュレーションの正確性も高まることになりますし、(これを言ってしまうと元も子もないかもしれませんが)何より近年の増配傾向を受けてうれしい気持ちで投資ができていて、株式投資へのモチベーション維持に繋がっているというのが高配当株投資を行っている最大の理由です。
2 配当金増加による生活水準向上
上述のとおり、高配当株投資であれば単年度ごとに利益が実現していきますし、5月中下旬までには3月決算企業の決算短信が出揃うため、当年度の配当金の受取額を見込むことができるようになります。
これまでも記載してきたとおり、わたしは毎年600万円を貯蓄することにしており、この600万円は「新規株式投資400万円+配当金再投資+残額」としています。したがって、配当金が増えれば給与所得からの貯蓄を減らすことができて、自由に使えるお金が増えることになります。
新規株式取得は税引後の取得利回り3%超を自主ルールとしていますので、「新規投資400万円+配当金再投資」によって税引後の配当金は来年度では16万円強増えることになりますし、来年度以降は配当金再投資額が増えた分、配当金の増加額も数千円ずつ増えていくことになります(分かりづらかったらすみません)。
自由に使えるお金が年間16万円増えるというのは、給与所得に置き換えれば「月給が1万3千円増える」ということですし、配当金再投資額が増えればこの増加幅も増えていく点もうれしいところです(非常に緩やかながら二次関数的です)。
やっぱり、投資をするからには日々の生活に潤いを与える要素があってほしいところで、この点も高配当株投資によるものかなと思います。
3 個別株の面白さ
続いては、個人の感性や好みの要素が非常に強くなりますが、「個別株の面白さ」というのもわたしが高配当株式を行う要因の一つです。
7月初旬にトヨタ自動車(7203)の株式を買ったところですが、やはり国内トップ企業としての憧れがあり以前からチラチラ眺めていました。
わたしが大学生だった頃に(約20年前!)に同級生から「トヨタ自動車の株を持っててだいぶ値上がりしたんだよね~」との話を聞いて、「学生で株式投資をするなんてスゴい!」と感心して今でもずっと覚えていたりします。
また、商業系の大学でもあったからか「投資同好会」のような集まりもあって一度参加したときには自動車業界について議論していました。当時の生産台数はざっくりトヨタ自動車が1,000万台、ホンダや日産が400万台、当時は生き残りをかけた合従連衡が進むなかで世界的にも1,000万台を目指す雰囲気があり「1,000万台クラブ」のような言葉が使われていて、「同じ学生なのに社会のことをこんなに興味を持って知ろうとしている人たちがいるのか」と衝撃を受けました。
と、トヨタ自動車1社だけで色々と書いてしまいましたが、そんな企業の株式を持てるようになったのは感慨深いところです。
とは言え、こうした個別企業ごとのエピソードに基づいて株式を取得しているわけではなく、単純に配当利回りの良い企業を並べたうえで、過去の業績や配当金の推移を見ながら銘柄を選んでいるのが基本です。
過去10年ぐらいの業績や配当金の推移、過去5年ぐらいのチャートの形、PERやPBRなどの指標を確認したうえで、気になる銘柄があれば決算短信を見て当期業績予想が不調であったりしないか、決算説明資料に気になる点がないかなどを確認しながら選定しています。
基本はバイアンドホールドなので(買ったら売らずに持ち続ける)、本来はじっくり企業分析する必要があるかもしれないですが、実際のところはそこまでやれてはいません。
上記のとおり企業分析の深度は浅いだろうという自覚はありつつも、そんなこんなで投資銘柄数は60を超えているところです。
近年の株主還元圧力の高まりによって増配する企業が増えているなか、高配当株投資を行っていると、5月上中旬には3月決算企業が決算短信を開示して配当予想が出てきますので、配当金の見込みを集計するのが非常にワクワクします。
また、「含み益は資産としてカウントしない」と記載しておいてなんですが、やはり保有している株式の株価が上昇するとうれしくもあります。日経平均を上回って上昇すれば業種や個社固有のプラス要因であると捉えて良いと思われ、業績好調によって将来の配当金の増額に繋がる可能性があるとも考えらえると思います。当然、日経平均対比でアンダーパフォームする(ベンチマークを下回る)こともあるでしょうし業績不振などにより株価が下落することもあり、プラスとマイナスの両面があります。
そうした個別企業の揺らぎが人によってはストレスになることもあるかもしれませんが、わたしにとっては楽しみになったり、ベンチマークとしている日経平均対比で成績の良し悪しが出ることで株式投資にハリが出てくると感じています。
実際、日産自動車(7201)や中国電力(9504)のように残念ながら振るわない銘柄もありますが、MUFG(8306)やSWCC(5805)のように配当金も株価も大幅に伸びた銘柄もあり、銘柄ごとに明暗がくっきり分かれるのも面白いところです。
4 自前での分散化と投資信託化
最後に、わたしの株式投資の状況を前提とすれば、「自前での分散化と投資信託化」という面もあるかと思っています。
現在は61銘柄に投資しており、当然ながらこのなかではなるべく業種の偏りが出ないようにしています。例えば金融機関などは高配当な傾向にあって飛びつきたくなるのですが、金融機関ばかり買い進めてしまっては金融業界が不調になった場合に大きな痛手となる可能性があります。また、取得額ベースでは1銘柄あたり50~70万円としていますので、銘柄間での金額の偏りも抑えるようにしています(取得後に株価が4~5倍になった銘柄もあり評価額ベースでの偏りは生じていますが、それはやむを得ないものとしています)
したがって、わたし自身は61銘柄への投資を通じて「国内高配当株式」をテーマとした投資信託を自前で組成しているのと同じ状況なのかなと捉えています。
近年は投資信託の信託報酬は安くなってきていますが、そうは言ってもそれなりに取られるかと思います。例えば信託報酬が0.5%であるとすると、税引後3%の利回りを目指すうえでは非常に大きな数字です。自前で多数に投資するポートフォリオ(資産構成)を構築すれば、投資信託のように高配当というテーマに沿ったうえで銘柄の分散を効かせることができますので、信託報酬を払う必要がなく税引後利回り3%の目標との距離が遠くならずにすむことになります。
最後に
わたしがインデックス投資ではなく高配当投資を行う理由は上記で挙げた4つが主なものですが、実際にはそれ以外にも色々あるかもしれません(例えば、わたしは個別株投資から入ったので今さら投資スタイルを大きく変えたくないといった面もあります)。
株式投資においてわたしが最も重要であると考えているのは、「市場から脱落しない」ということであり、いかに投資を継続することができるかという点に尽きるかと思います。
そのため、ここで記載したのはあくまで「わたしにとって」投資を継続するにあたってのモチベーションに焦点が当たっているものとして理解してもらうのが良いかと思います。
最も良い投資スタイルは個人によって区々であり、それはなぜなら投資を続けたいと思う動機やモチベーションは最後は人の気持ちによるものであって各個人によって異なると考えらえるからです。
したがって、ここで書いたことはあくまで1つの考え方や意見であり、自分なりの考えを固めていくうえでの参考として捉えてもらえればと思います。
今回も非常に長文となりましたが、ここまでお読みいただいてありがとうございました。
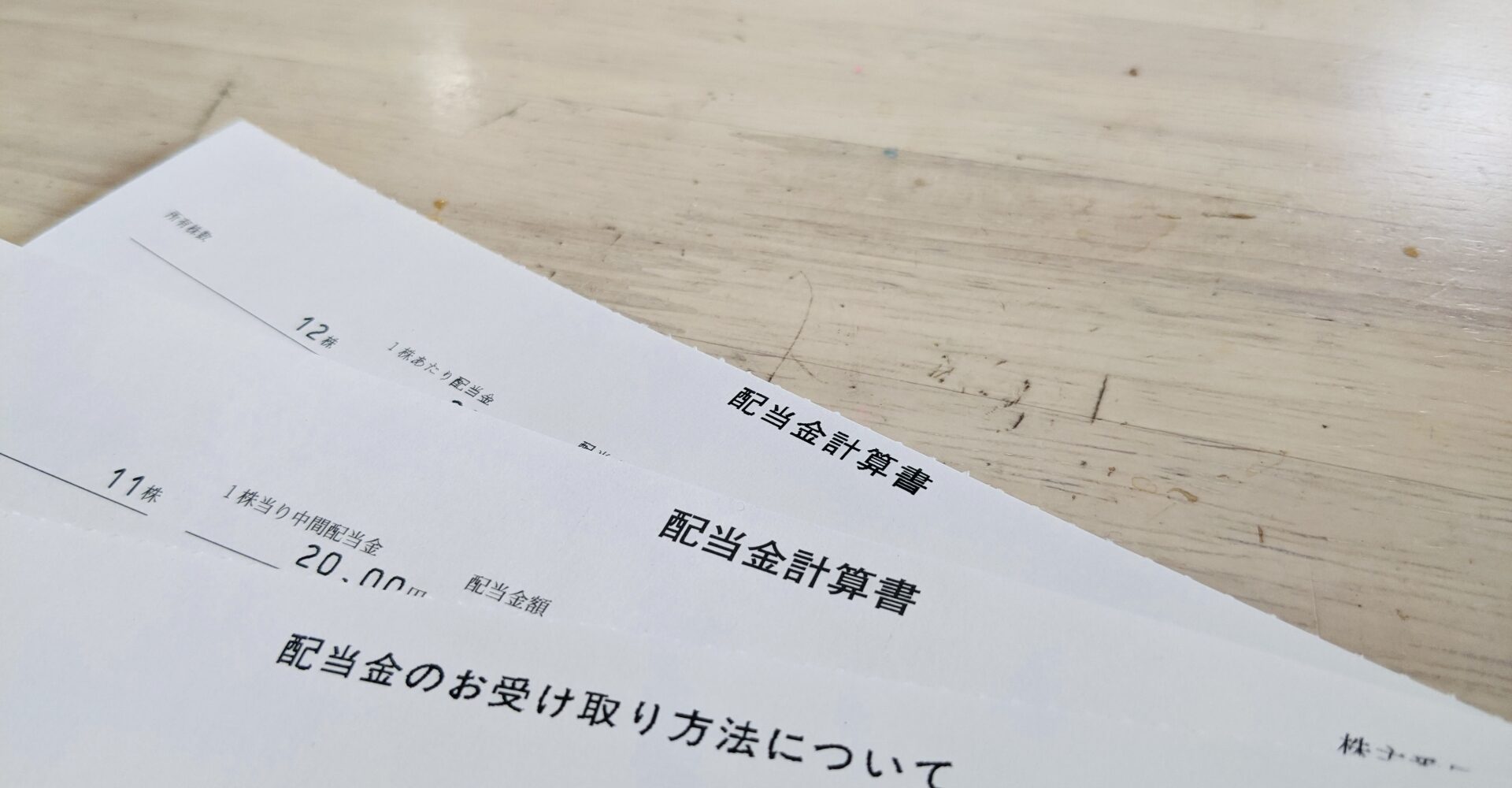
-e1750861693764-120x68.jpg)